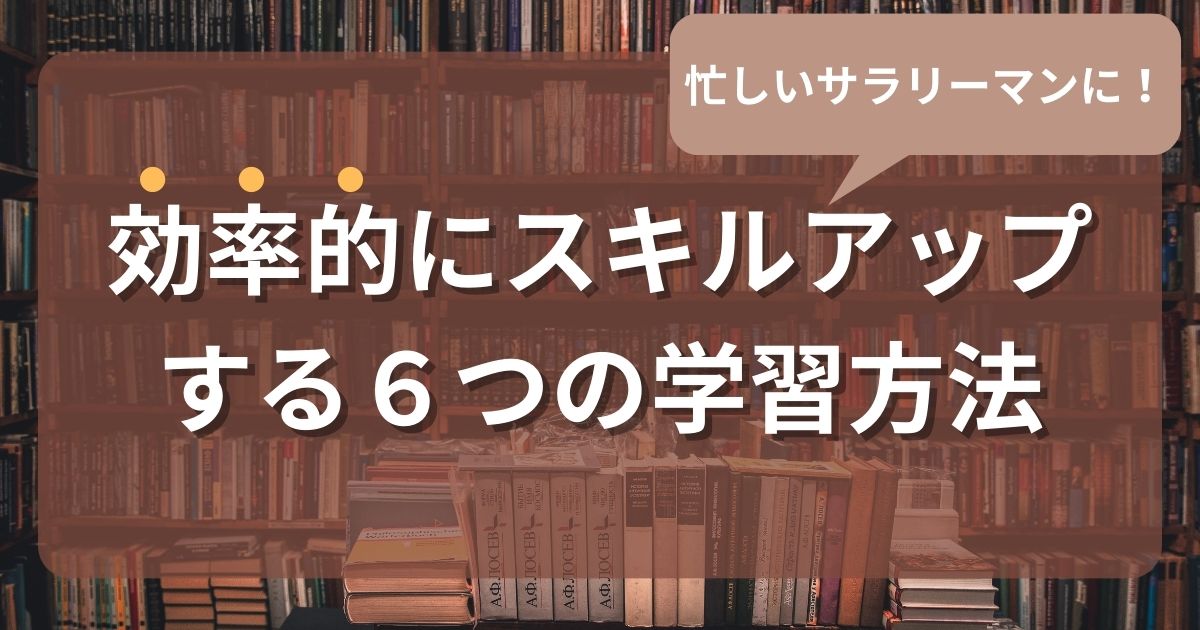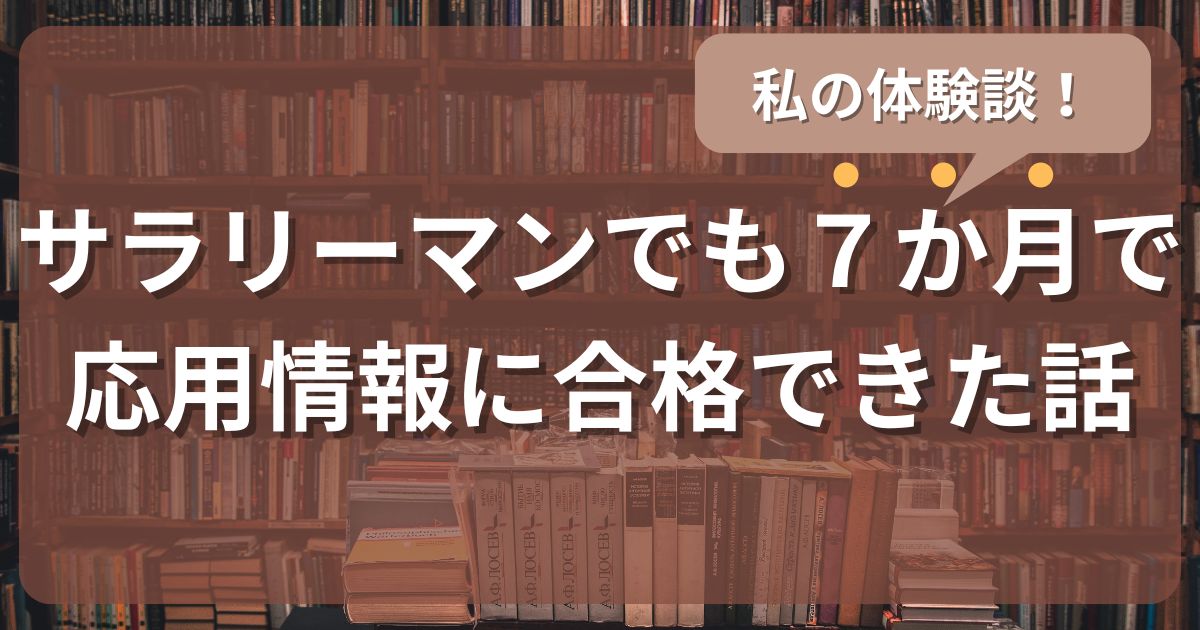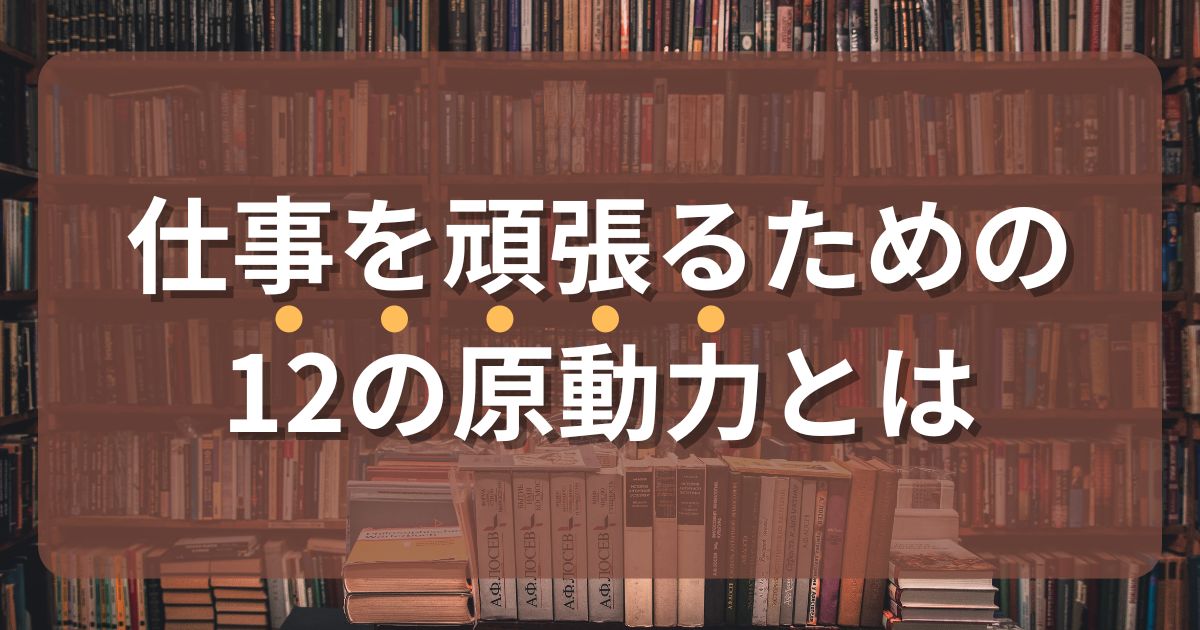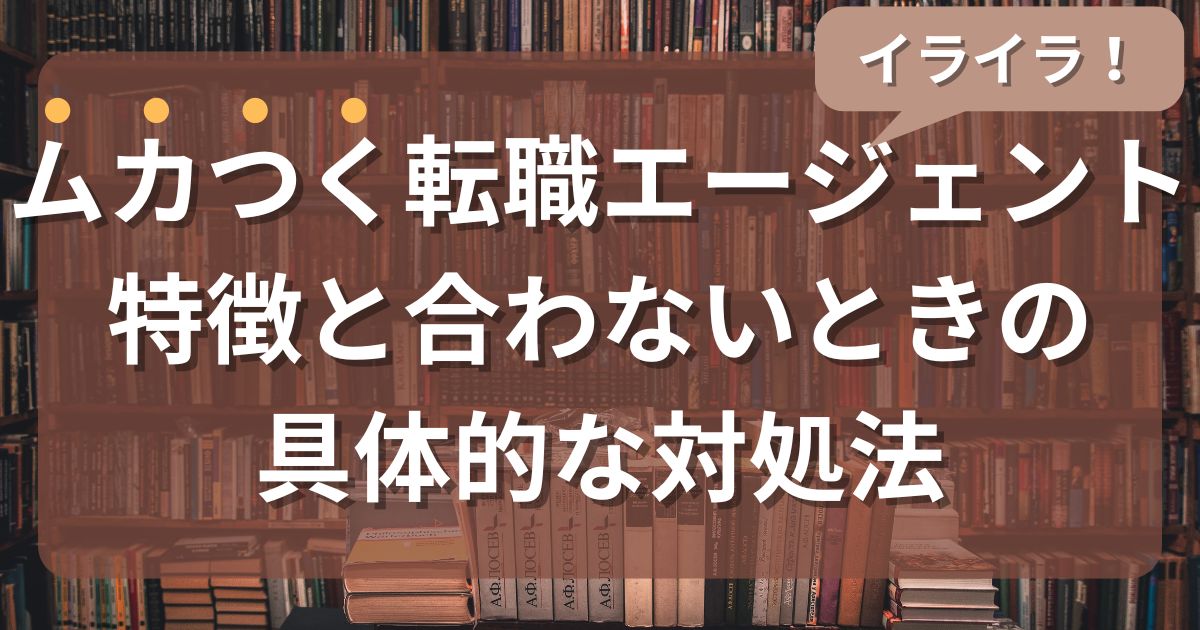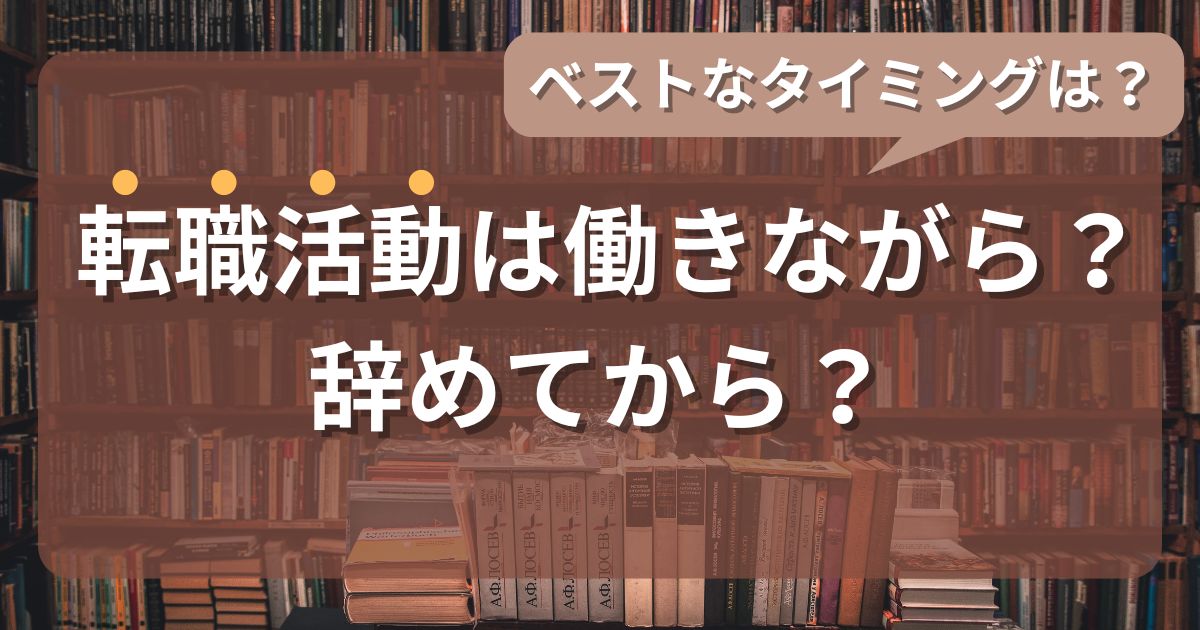出世だけが正解じゃない?現代におけるキャリアの選択肢一覧を紹介
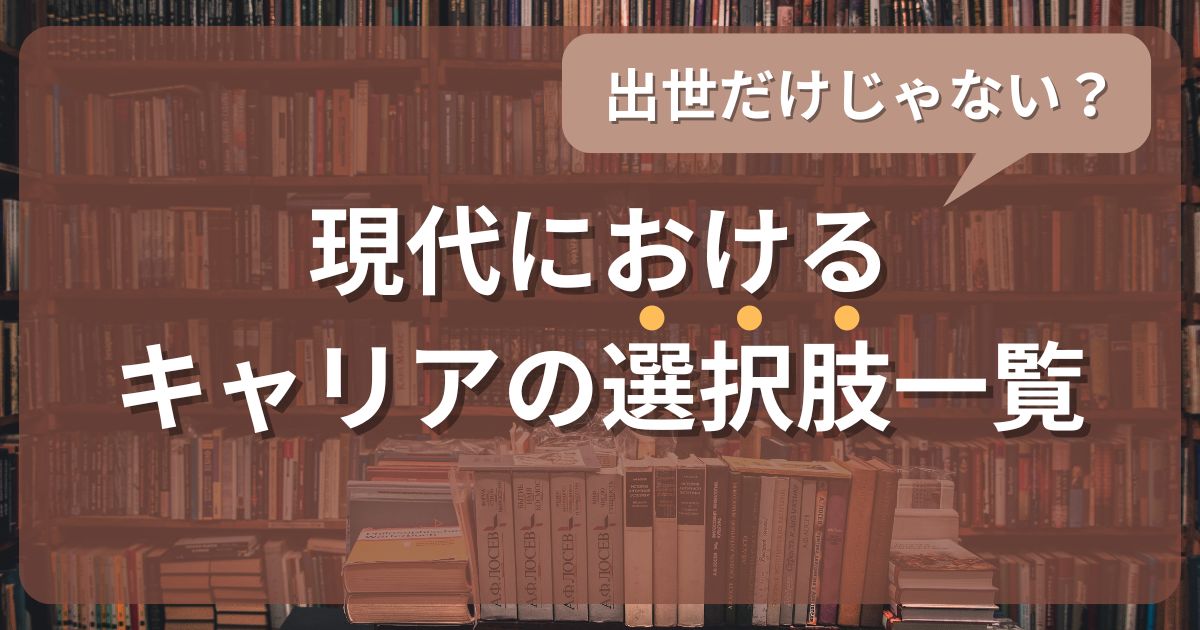
おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。
本日は、今のキャリアに悩んでいる方に、出世だけではない現代におけるキャリアの選択肢一覧を紹介します。
- どのようなキャリアの選択肢があるか知りたい
- 今のままのキャリアで良いのか悩んでいる
- 自分のキャリアの幅を広げたい
はじめに:「出世=成功」はもう古い?価値観の多様化が進む時代へ
かつては出世こそがキャリア成功の象徴でしたが、いまやその価値観は大きく変わりつつあります。
管理職を目指す人が減少し、仕事と私生活のバランスや、自分らしさを大切にした働き方に注目が集まっているのです。
背景には、終身雇用の崩壊やリモートワークの浸透など、社会構造そのものの変化があります。
また、SNSや副業の広がりによって、個人の力で生計を立てる道も身近になりました。
「キャリア=出世」という一辺倒な考えから離れ、多様な働き方や生き方を選べる時代が到来しているのです。
本記事では、そんな時代に合ったキャリアの選択肢を、具体例ととも紹介します。
かつての「理想のキャリア」とは?
では、具体的なキャリアの選択肢を紹介する前に、理想のキャリアの変化を見ていきます。
これまでの理想のキャリアはどのようなものだったのでしょうか?
まずはその実態を見ていきます。
年功序列と終身雇用が前提だった昭和型キャリア
昭和から平成初期にかけて、日本のビジネス社会では年功序列と終身雇用が当たり前でした。
若いうちは下積みを重ね、年齢や勤続年数に応じて昇進・昇給するのが当たり前。
新卒で入った会社に定年まで勤めあげることが美徳とされ、そのなかで管理職を目指すのがキャリア成功と考えられていました。
企業側も「一度採用した人材は最後まで面倒を見る」ことを前提に人事制度を設計しており、転職や異動はむしろリスクとされていた時代です。
このような環境では、「とにかく我慢して続けること」が求められ、自分の適性や希望よりも会社の都合が優先される風潮が根強く存在していました。
「管理職=勝ち組」とされた時代
かつて管理職は、高収入と安定の象徴でした。
部長・課長といった肩書は、出世競争を勝ち抜いた証であり、周囲からの評価や社会的な信用にも直結していたのです。
特に大企業では、管理職に就くことで住宅手当や家族手当などの福利厚生が厚くなり、将来の年金額にも差がつく仕組みでした。
そのため、「出世しない=損」という意識が一般的だったのです。
また、終身雇用のなかでキャリアを積むためには、組織内での昇進がほぼ唯一の選択肢とされていたことも背景にあります。
一方で、マネジメントに向いていない人や、部下を持ちたくない人も管理職になるしかなかったという側面もあり、結果的に無理に適性外のポジションに就かざるを得ないケースも多かったのです。
「転職=逃げ」だった過去の常識
少し前までは、転職は「何かに失敗した人がするもの」といったネガティブなイメージが根強くありました。
新卒で入社した会社を途中で辞めることは「根性がない」「逃げた」と見なされ、履歴書に空白期間があるだけで採用を見送られることも珍しくありません。
企業側も中途採用に消極的で、育成はすべて新卒からという方針が一般的でした。
しかし近年は、転職市場が活発化し、スキルや経験をベースにキャリアを築く人が増加しています。
「よりよい環境を求めて主体的に動く人」という評価に変わってきています。
なぜ今、キャリアの選択肢が増えているのか
では、なぜ現代ではキャリアの選択肢が増えてきたのでしょうか?
これまでの終身雇用を前提としたキャリアから現代にかけてどのように変わってきたのかを見ていきましょう。
終身雇用制度の崩壊とジョブ型雇用の浸透
かつて日本では「会社に勤め続ければ一生安泰」という終身雇用制度が主流でした。
しかし、バブル崩壊以降、企業の業績悪化やグローバル競争の激化により、定年まで雇い続ける前提が崩れ始めました。
近年では「ジョブ型雇用」が広まりつつあり、ポストに必要なスキルを持つ人を登用する流れが強まっています。
これは欧米的な働き方に近く、職務内容に応じて人材を選ぶスタイルです。
この変化により、企業内での出世だけに頼らず、スキルや経験を武器に社外でも価値を発揮できるキャリアが求められるようになってきました。
結果として、一つの会社に縛られない働き方や、自らキャリアを選び直す人が増えてきているのです。
副業・フリーランスの増加
働き方改革の影響や、テクノロジーの進化により、副業やフリーランスとして働く人が急増しています。
かつては会社員が副業を行うことは就業規則で禁じられているケースがほとんどでしたが、現在では副業を容認・推奨する企業も増えてきました。
フリーランスとしても、クラウドソーシングやSNSの普及によって、案件を獲得する手段が広がり、個人が企業と対等に取引することが可能になっています。
ライター、デザイナー、エンジニアなど専門性のあるスキルを持つ人が、個人事業主として働く事例も一般的になりつつあります。
こうした動きは、「一社に依存しないキャリア」の可能性を広げ、多様な働き方の選択を後押ししています。
ライフスタイル重視の価値観の広がり
従来の「仕事第一」の価値観から、「自分らしく生きたい」「家族との時間を大切にしたい」というライフスタイル重視の意識が広まりつつあります。
特にコロナ禍をきっかけに、多くの人が生活や働き方を見直すようになりました。
都市部での消耗戦から離れて地方に移住したり、フルタイムではなく短時間勤務を選んだりするなど、生活スタイルに合わせたキャリア選択が注目されています。
こうした傾向は特定の世代に限らず、子育て世代やミドル世代、シニア層にも広がりを見せており、「人生をどう生きたいか」という価値観がキャリア選択の軸になってきています。
収入よりも幸福度を優先する風潮が、働き方をより柔軟にしているのです。
働き方改革やリモートワークの影響
2019年以降の働き方改革や2020年以降のパンデミック対応により、テレワークや時差出勤が一気に普及しました。
これにより「場所や時間に縛られない働き方」が現実的な選択肢となり、キャリアの可能性は一気に広がりました。
たとえば、地方に住みながら都内の企業でリモート勤務する、育児中の親が在宅で働くといったことが当たり前になりつつあります。
また、出社頻度が減ることで副業や学び直しに時間を割く人も増え、会社外でのスキル構築が加速しています。
企業側も成果重視の評価制度を取り入れ始め、従来の「長時間働く人が評価される」体制からの脱却が進んでいます。
これらの流れが、出世しか選択肢のなかったキャリア観に風穴を開けているのです。
多様化するキャリアの選択肢一覧
ではそのような多様化するキャリアの選択肢についてどのようなものがあるのでしょうか?
ここではそんなキャリアの選択肢を一覧にして紹介します。
選択肢①:今の会社で出世を目指す
従来から根強く支持されているのが、「今の会社で出世を目指す」キャリアパスです。
これは企業内での昇進を通じて責任あるポジションに就き、収入や影響力を高めていく方法です。
特に大手企業や安定した組織では、評価制度や福利厚生が整っており、出世によって長期的な安定と社会的な信用を得られるメリットがあります。
マネジメント経験や組織運営のスキルを身につけられることも大きな強みです。
一方で、昇進競争や過重労働のリスクもあるため、自分の価値観やライフスタイルに合うかどうかを慎重に見極めることが重要です。
とはいえ、確実なキャリアパスの一つとして、今なお多くの人が志望し続けている選択肢であることは間違いありません。
選択肢②:専門スキルを極める
一つの分野に特化し、専門性を高めていく「プロフェッショナル型」のキャリアは、出世とは異なる成功の形として注目されています。
例えば、ITエンジニアや税理士、Webデザイナーなどは、企業に所属していても個のスキルで評価される傾向が強いものです。
こうした職種では、管理職にならなくてもスキルに応じた高収入や働き方の自由を得ることができます。
また、資格や実績を積み上げることで市場価値が高まり、独立や転職でも有利になることができるのです。
特にAIやデータ分析、などの分野は今後も需要が高まるとされています。
「職位よりも技術」を重視するキャリア志向は、今後さらに一般化していくでしょう。
選択肢③:転職でキャリアを積み上げる
一つの会社にとどまらず、複数の企業を経験しながらキャリアを構築する「ジョブホッピング型」も、現代ではポジティブな選択肢と捉えられるようになってきました。
特に20〜30代の若手層では、「スキルアップのための転職」は前向きな行動とされ、異なる業種や職種を渡り歩くことで視野や経験を広げています。
たとえば、営業職からマーケティング職へ転向したり、大手企業からスタートアップに転職したりと、柔軟なキャリア形成が可能です。
転職によって待遇改善やキャリアアップが実現できるケースも多く、自分に合った働き方や会社の文化を見つける手段として有効になっています。
転職市場の活性化が、この動きを後押ししています。
選択肢④:地域や家庭に根ざす
都会での出世競争を離れ、地方や家庭を軸にした働き方を選ぶ「ローカル志向型」も広がりを見せています。
特にコロナ禍以降、地方移住を選択する人が増え、地元の企業や自治体と関わりながら仕事をするスタイルが一般的になりつつあるのです。
農業や観光業、地域ベンチャーなどで働くケースや、地域おこし協力隊などを通じて地域に貢献する生き方も注目されています。
また、育児や介護と両立しやすい仕事を選ぶことで、家族との時間を優先したキャリア設計も可能です。
年収や肩書ではなく、「どんな暮らしをしたいか」「どこで生きていきたいか」といった価値観が、キャリアの選択基準として重視されるようになってきました。
選択肢⑤:副業・複業を活かす
一つの職業に依存せず、複数の収入源を持つ「パラレルキャリア型」は、リスク分散と自己実現を両立できる選択肢として注目されています。
たとえば、平日は会社員として働きながら、週末はライターやコンサルタント、副業カフェの運営などを行うスタイルです。
収入面の安定だけでなく、「本当にやりたいこと」に挑戦できる点も魅力です。
また、会社側も副業を通じたスキルアップや視野の拡大を期待して、副業を解禁する動きが進んでいます。
複業によって、自分の市場価値を試す場が増えるだけでなく、将来的な独立や転職にもつながることから、特にミドル層を中心に新たなキャリア戦略として広まりつつあります。
選択肢⑥:スローライフを重視
仕事中心の生活から離れ、心のゆとりや健康を重視した「ゆるキャリ志向」も、現代のキャリアの一つです。
出世や高収入よりも、自分のペースで働ける環境や、趣味や家族との時間を大切にすることに価値を見出す人が増えています。
たとえば、正社員ではなく契約社員や派遣社員としてあえて働き方を限定したり、週3勤務や時短勤務を選んだりすることで、生活の質を保ちながら働くというスタイルです。
特に精神的な健康やストレスとのバランスを重視する人にとっては、持続可能な働き方といえるでしょう。
「がむしゃらに働く時代」から、「自分らしく生きる時代」へと、社会全体の価値観が変化していることが背景にあります。
選択肢⑦:フリーランスとして生きる
会社に属さず、個人として業務を請け負う「フリーランス」という働き方は、以前に比べてずっと身近な選択肢になりました。
特にIT系やクリエイティブ職では、クラウドソーシングやSNSを通じて仕事を獲得できる環境が整いつつあります。
たとえば、Webエンジニアや動画編集者、ライターなどは、在宅で仕事が完結することも多く、働く場所や時間を自由に選べる点が魅力です。
会社員よりも収入が不安定になるリスクはありますが、報酬単価を自分で交渉できるため、実力次第で大きな収入アップも期待できます。
時間や人間関係のしがらみから解放される一方で、自己管理能力や営業力も問われるため、自己主導でキャリアを築きたい人に適した選択肢です。
選択肢⑧:起業・スタートアップへの挑戦
自らビジネスを立ち上げる「起業」や、成長途上の企業に飛び込む「スタートアップ参画」も、出世とは異なるキャリア成功の一つです。
起業では、アイデアを形にして世の中に価値を提供できる喜びがありますし、スタートアップ企業では若いうちから裁量権を持ち、スピード感のある成長環境で働ける魅力があります。
副業で始めた小さなビジネスが軌道に乗って独立するケースも増えています。
失敗のリスクはありますが、その分得られる経験や人脈、スキルは大きく、再挑戦がしやすい社会環境も整いつつあります。
特に「自分で道を切り開きたい」「挑戦する生き方をしたい」と考える人にとっては、非常にやりがいのあるキャリアの選択肢といえるでしょう。
選択肢⑨:ギグワークやプロジェクト単位で働く
企業に長く勤めるのではなく、単発・短期の案件ごとに働く「ギグワーク」や「プロジェクトベース」の働き方も拡大しています。
Uber Eatsの配達員やタスク系アプリを活用した働き方がその代表例ですが、近年では高度な専門性を求められる業務にもギグワークの形が広がっています。
企業のDX支援や新規事業立ち上げに、プロフェッショナル人材として数カ月単位で関わるケースなどです。
このような働き方は、自分の強みや得意分野を活かしながら、さまざまな企業や業界を横断的に経験できるというメリットがあります。
安定性よりも柔軟性や自己裁量を重視する人にとって、有効なキャリア形成のひとつです。
まとめ
本日は、今のキャリアに悩んでいる方に、出世だけではない現代におけるキャリアの選択肢一覧を紹介しました。
- 選択肢①:今の会社で出世を目指す
- 選択肢②:専門スキルを極める
- 選択肢③:転職でキャリアを積み上げる
- 選択肢④:地域や家庭に根ざす
- 選択肢⑤:副業・複業を活かす
- 選択肢⑥:スローライフを重視
- 選択肢⑦:フリーランスとして生きる
- 選択肢⑧:起業・スタートアップへの挑戦
- 選択肢⑨:ギグワークやプロジェクト単位で働く
かつては「出世=成功」という考え方が当たり前でしたが、今やキャリアの価値観は大きく変化しています。
働き方が多様化し、一つの会社で昇進を目指す以外にも、専門スキルを磨く、転職を重ねる、地方でのんびり働く、副業でやりたいことに挑戦するなど、無数の選択肢が広がっています。
どの選択が正解かは人それぞれであり、重要なのは「自分にとって何が心地よく、満足できる働き方か」を見極めることです。
キャリアの軸を出世に限定するのではなく、自分の価値観やライフスタイルに合った道を選ぶことこそが、これからの時代における本当の「キャリアの成功」と言えるのではないでしょうか。
以上、タカヒデでした。