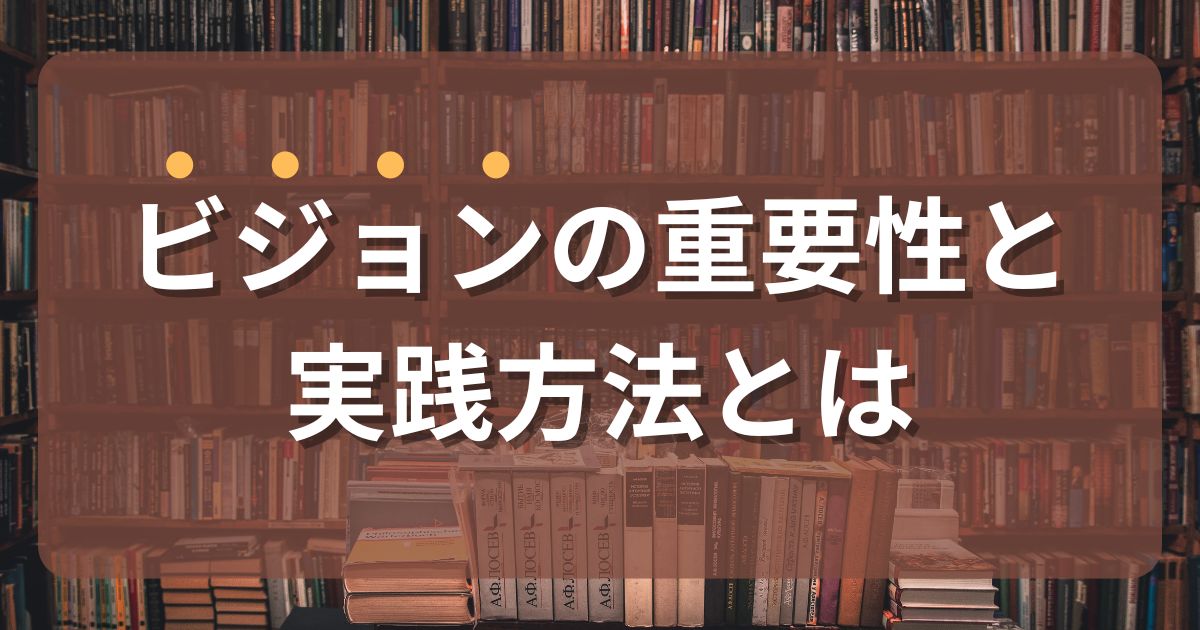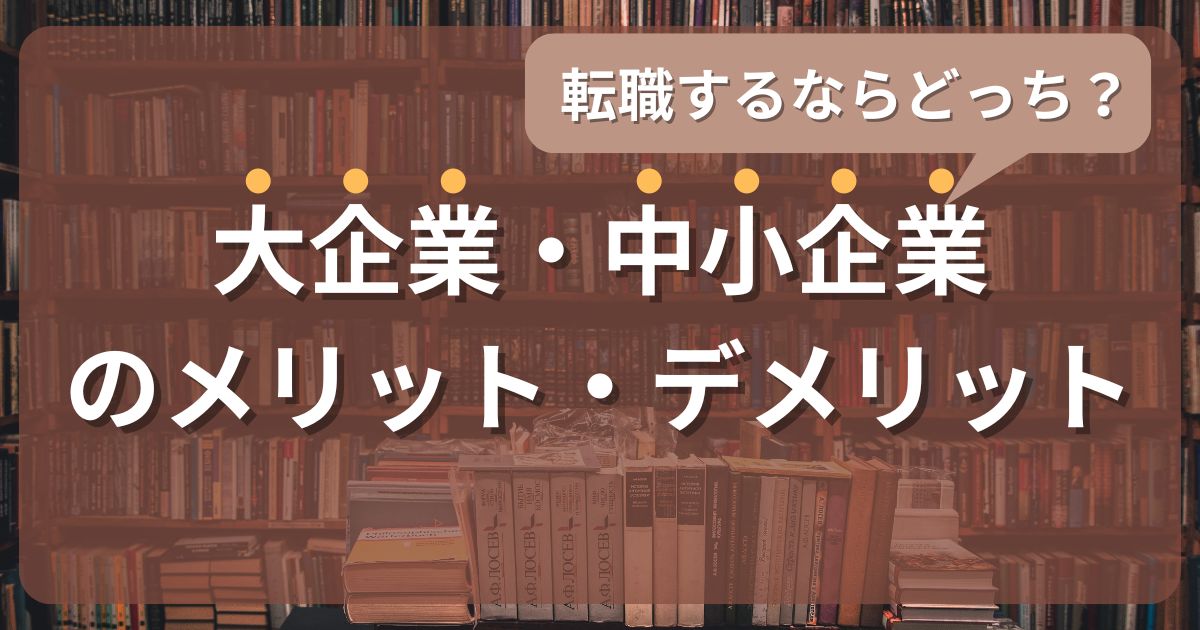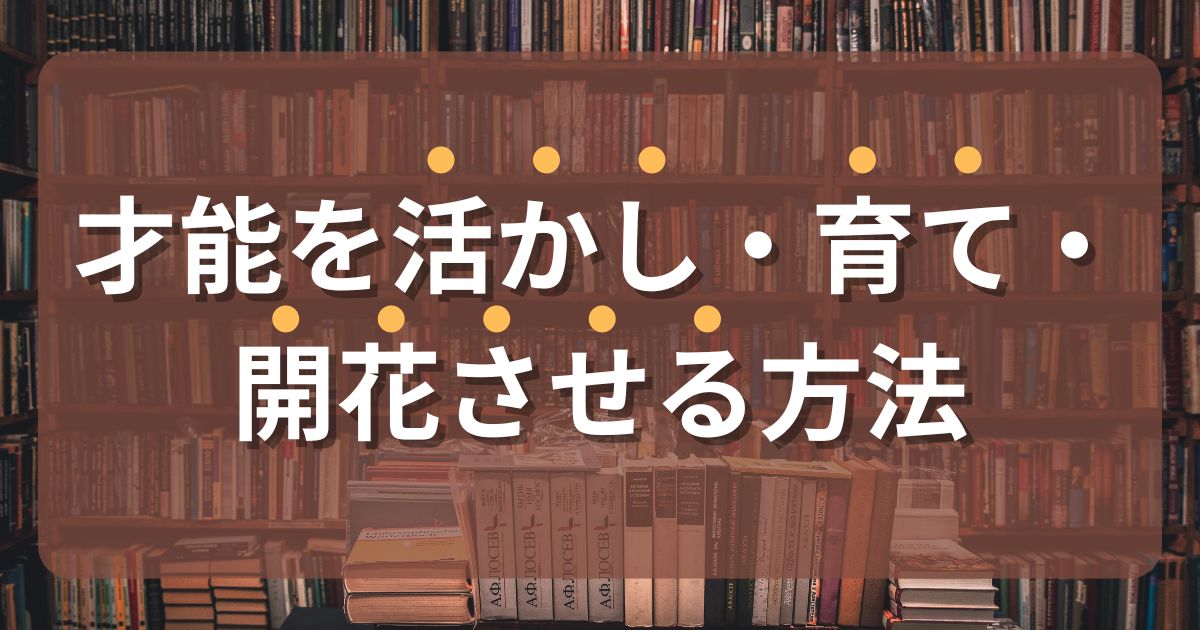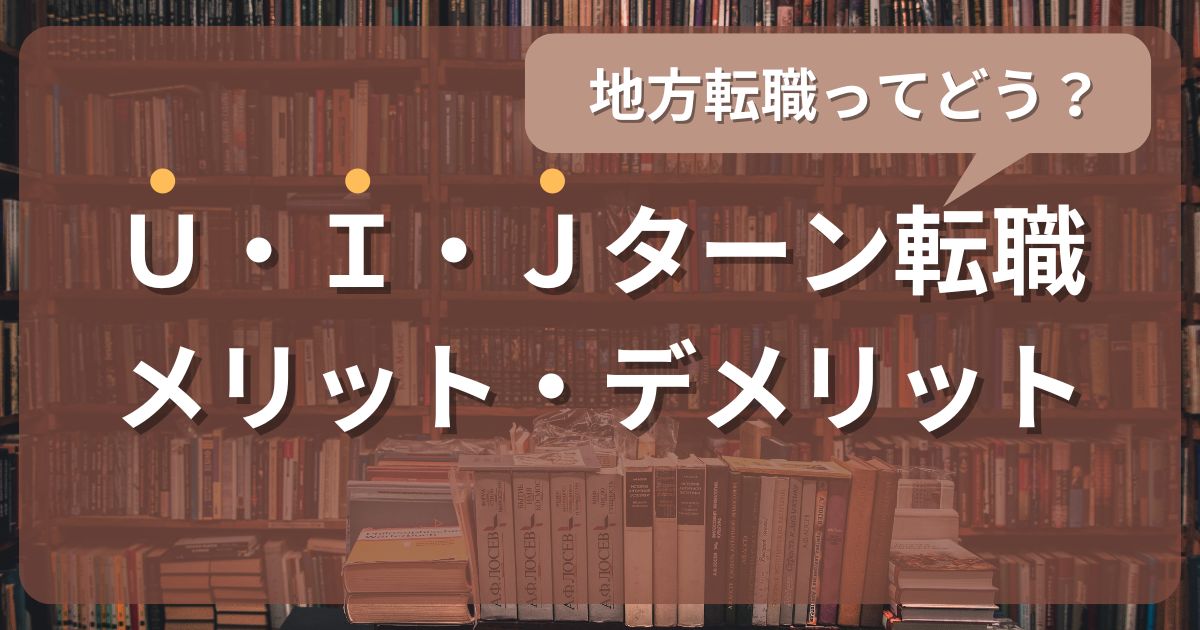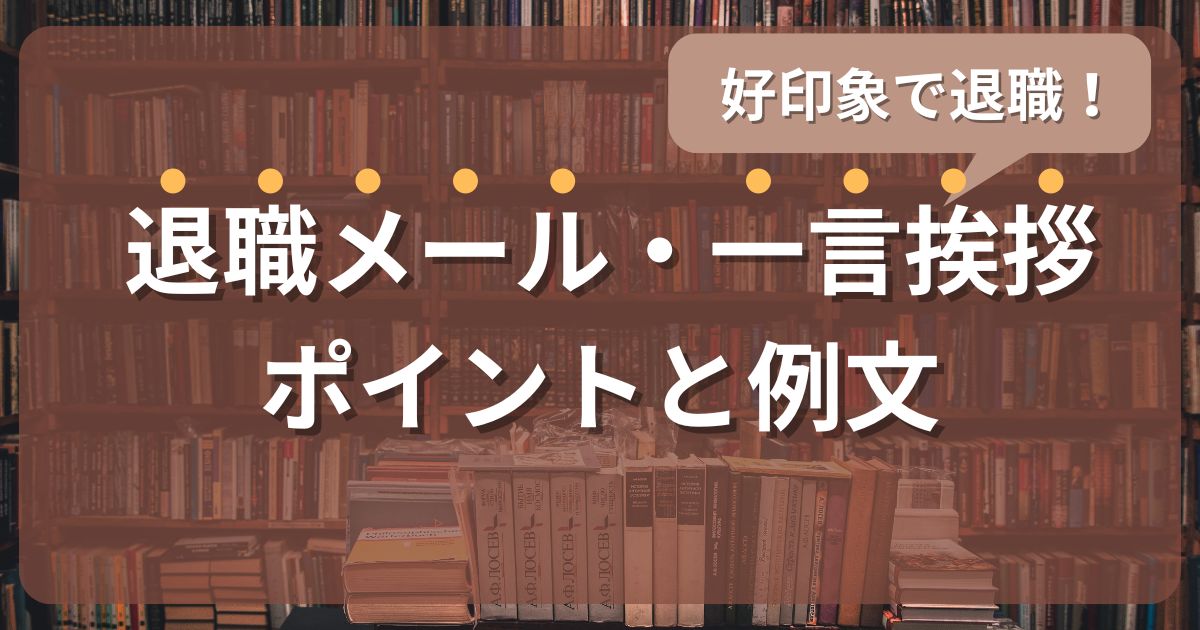リストラされないために!会社が求める人材の特徴とは?求められる人材になるためのポイント
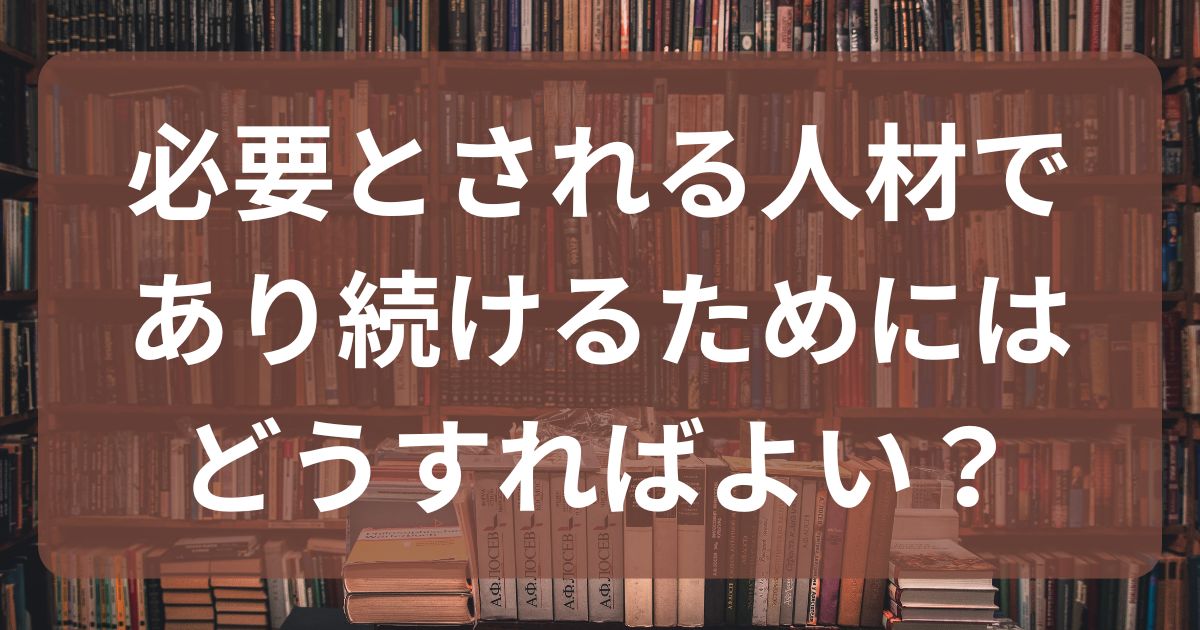
おはようございます。キャリアに悩む30代タカヒデです。
本日は、仕事に頼りにされなくて不安な人に、会社から求められる人材になるための方法を紹介します。
- 必要とされる人材になりたい
- やりたいことが見つからない
- どのようなキャリアを進むべきか分からない
はじめに
かつては、会社に入社してまじめに働き続けていれば、自然と昇進し、安定した生活が保証される時代がありました。
しかし、現代はそういった「保証のある時代」ではなくなりつつあります。
終身雇用制度の崩壊、デジタル化の急速な進行、により、働き方は多様化するようになりました。
企業は一人ひとりの社員に対して「何ができるか」「どんな価値をもたらせるか」をよりシビアに見るようになったのです。
つまり、「ただ在籍しているだけ」では評価されない時代なのです。
この記事では、会社から本当に必要とされる人材とはどのような人か、そして自分自身がそのような人材になるためには何を意識すべきかを解説します。
変化の激しい時代だからこそ、個人としての価値を高めるヒントを掴んでください。
なぜ会社から求められる・必要とされる人材にならないといけない?
冒頭も一部お伝えした部分ですが、そもそもなぜ「会社から求められる」ような、「必要とされる」ような人材になられければならないのでしょうか?
まずはここで4つの理由を紹介していきます。
理由①:終身雇用の終了
かつては「一度就職すれば定年まで安心」という時代がありましたが、現在ではその常識が崩れつつあります。
大手企業ですら早期退職制度や人員削減を進め、終身雇用はもはや過去のものになりつつあるのです。
この背景には、日本全体の経済成長の鈍化や、グローバル競争の激化があり、企業が人件費を最適化せざるを得ない状況が続いています。
そのため、ただ在籍しているだけの人材では生き残れない時代に突入しました
会社が今、求めているのは「価値を生み出す人」です。
つまり、変化に対応し、組織に貢献できる人材でなければ、たとえ勤続年数が長くても立場は安泰ではありません。

あの「トヨタ自動車」ですら「終身雇用守るの難しい」という発言があったほどだよね…
理由②:技術の進化、デジタル化の加速
AI、IoT、クラウド、RPAなどの技術がビジネスに急速に取り入れられています。
例えば、製造業では自動化によって単純作業の多くが不要となり、事務職でもRPAにより定型業務の自動化が進んでいます。
こうした流れの中で、旧来のスキルだけでは通用しない場面が増えています。
今や「技術を使いこなせる人」や「新しい仕組みを理解して業務改善できる人」が求められているのです。
ITリテラシーが高く、自ら学ぶ姿勢を持った人は、それだけで他の社員と差別化され、価値ある存在として認識されます。
もはや「知らない」では済まされないのが現実となったのです。
理由③:業務委託やフリーランスなどの働き方の多様化
働き方の選択肢が増え、会社は必ずしも社員を抱える必要がなくなりました。
たとえば専門性の高い業務であれば、業務委託やフリーランスに外注したほうがコストやスピードの面で優れることもあります。
つまり、正社員であること自体に価値があるのではなく、「この人に任せたい」と思わせる能力や実績が重要なのです。
結果として、企業は社員に対しても「外部人材よりも価値を発揮できるか」を厳しく見ています。
働き方が多様化した現代では、「与えられた仕事をこなすだけ」の人材は生き残れません。
自分の強みを発揮し、付加価値を示せる人が求められています。
理由④:人の期待にこたえなければ会社での居場所を失ってしまう
会社はチームで動く組織です。
組織内での信頼や評価は、「他者の期待に応える」ことで築かれます。
逆に、期待に応えられないと「成果を出せない人」「頼りにならない人」というレッテルを貼られ、プロジェクトから外されたり重要な仕事を任せてもらえなくなったりする可能性があります。
たとえば、納期を守る、報連相をしっかり行う、周囲と協調する姿勢を見せるなど、小さな信頼の積み重ねが評価につながります。
人の期待に応え続けることができれば、組織内での存在感が増し、結果として「必要な人材」として認められるのです。
会社が求める人材の特徴とは?
では、具体的には、どのような人を会社は求めるのでしょうか?
今度はその特徴を見ていきます。
特徴①:自ら考え行動に移す積極性がある
現代の企業では、指示待ちの姿勢よりも「自ら課題を発見し、提案・実行できる人材」が強く求められています。
たとえば、業務の中で非効率な部分を見つけ、上司に相談のうえで改善策を講じた社員は高く評価される傾向にあります。
これは会社側にとって、放置すれば損失になりかねない問題を未然に防げるからです。
また、積極性のある人は組織に活力を与え、周囲を巻き込んで前進させる力を持っています。
自律的に動ける人材はマネジメントの手間も減るため、企業としても重宝されるのです。
特徴②:柔軟な考え方で課題を解決することができる
変化の激しい社会では、過去の成功体験や固定観念に縛られていては立ち行きません。
たとえば、コロナ禍において対面営業が困難になった企業が、リモート商談へと切り替え売上を回復させた事例があります。
ここで活躍したのは、柔軟に考え、状況に応じて戦略を変えられた人たちです。
また、トラブル対応においても「一つのやり方しか知らない人」より「複数の視点で物事を見られる人」の方が迅速かつ的確に問題を解決できます。
今後の不確実な時代において、柔軟性は大きな武器になります。
特徴③:前提にとらわれずゼロから新しいものを作り出すことができる
イノベーションが求められる現代では、既存の枠組みにとらわれない発想力が求められます。
たとえば、UberやAirbnbのようなサービスは、これまで当たり前だった「タクシーは運転手のもの」「宿泊はホテルで」という概念を打ち破ったことで成長しました。
このように、「常識を疑い、ゼロから考える姿勢」を持つ人は、会社に新しい価値をもたらします。
何も大きな発明をする必要はありません。
日常の業務の中でも「今までと違うやり方に挑戦してみる」「仕組みそのものを見直す」ことができる人材は、企業にとって貴重な存在となることができます。
特徴④:一つのことを追求し続ける姿勢がある
成果を出すうえで欠かせないのが、粘り強く物事に取り組む力です。
たとえば、製品開発の現場では、何度も失敗を繰り返しながら改善を重ねていくプロセスが不可欠です。
ここで重要なのは、すぐに諦めず一つのテーマに対して根気強く向き合えるかどうかです。
追求力のある人は、最終的に周囲が想像できなかったクオリティや成果を上げることがあります。
また、専門性が必要なポジションにおいては、長期的な視野で技術や知識を深め続けられる人材こそが、組織にとって大きな戦力となります。
特徴⑤:他者と協力して物事を成し遂げることができる
どんなに優秀な人でも、チームプレイができなければ企業の中では評価されにくい傾向にあります。
なぜなら、会社は一人で完結する場ではなく、複数の人が関わり合いながら成果を出す場所だからです。
プロジェクトでは、部門をまたいだ連携が必要不可欠であり、報連相や配慮、調整力が問われます。
実際に、優れた成果を上げるチームには「自分の役割を理解しつつ、他者の意見にも耳を傾けられる人」が必ずいます。
協調性を持ち、共に成長しようとする姿勢は、組織の中で高く評価される資質の一つです。
特徴⑥:グローバル・多様性を受け入れる姿勢がある
近年では、海外との取引や多国籍チームの形成が当たり前になっており、価値観や文化の異なる人と協働できる力が求められています。
外国人スタッフと円滑にコミュニケーションを取れる社員や、LGBTQなど多様な背景を持つ人に配慮できる社員は、社内外で信頼を築くことができます。
また、多様性を受け入れられる人は、固定観念にとらわれず幅広い視点を持って物事を判断できるため、グローバルな環境下でも柔軟に適応できます。
これからの時代、「違いを尊重し共に働ける力」は大きな武器となります。
会社から求められる・必要とされる人材になるためのポイント
では、最後に、具体的に会社から求められる・必要とされる人材になるためのポイントを紹介します。
ぜひこのポイントを抑えることで、自身のキャリアアップ・スキルアップを実現させてください。
ポイント①:自分の価値を提供する相手・分野を決める
会社で価値ある存在になるには、「誰に・何を提供する人なのか」を明確にすることがスタート地点です。
たとえば、「営業部門に対して資料作成の効率化をサポートする」「IT部門で業務の自動化を推進する」など、自分が貢献する対象と分野を絞ることで、強みが見えやすくなり評価もされやすくなります。
闇雲に働くのではなく、「自分が最も力を発揮できる場面」を意識することが重要です。
これはマーケティングで言う「ターゲットと市場の選定」にあたる行為で、価値提供の土台を築くうえで必要不可欠です。
ポイント②:相手の求めることを解決する方法を決める
価値提供の相手が決まったら、次は「どんな手段でその人の課題を解決するのか」を明確にします。
たとえば、上司が求めているのは「早く・正確に資料を作ってほしい」であれば、Excelの関数やマクロを活用するのが一つの方法です。
また、業務改善が求められているなら、ヒアリング→課題整理→施策提案といったプロセスが有効です。
重要なのは、「相手のニーズに合った手段を選ぶ」ということ。
自分本位ではなく、あくまで相手目線で「何をどうすれば役に立てるのか」を考える姿勢が求められます。
ポイント③:自分の価値をコンテンツとして作り出す
目に見えない「自分の強み」や「得意なこと」も、アウトプットという形で表現することで、はじめて他者に伝わります。
たとえば、日頃の業務で得たノウハウをマニュアル化する、効率化した仕組みを社内ツールとして整えるなどは立派な「価値の可視化」です。
また、社内SNSや朝会などで「こういう工夫をして成果が出た」と発信すれば、自分のスキルや工夫を伝えるコンテンツになります。
自分の経験や考え方を蓄積・発信できる人は、組織にとって「知識の資産」となり、結果的に重宝される存在になります。
ポイント④:作り出した価値を伝える
どれだけ良い成果を出しても、それが周囲に伝わっていなければ「評価されない」という残念な結果になりがちです。
そこで重要なのが「成果を正しく伝える力」です。
たとえば、週報や報告書に「改善前と後の差」「取り組んだ工夫」「得られた結果」を整理して書くことで、上司や関係者に自分の価値が伝わります。
また、プレゼンや会議で簡潔にポイントを話すスキルも重要です。
伝えることは悪い意味の「アピール」ではなく、良い意味の「共有」です。
自分の取り組みが会社にどう貢献したのかを伝えることは、正当に評価されるための第一歩となります。

つまりは「会社に対してマーケティング」を行うイメージだね!
ポイント⑤:ポータブルスキルを身につける
ポータブルスキルとは、「業種や職種を問わず通用する汎用スキル」のことです。
たとえば「論理的思考力」「プレゼン力」「タイムマネジメント力」「ファシリテーションスキル」などが該当します。
これらのスキルは、部署やプロジェクトが変わっても発揮でき、組織を横断して活躍するための“武器”となります。
また、ポータブルスキルは転職市場でも高く評価され、個人としての市場価値向上にもつながります。
自分の強みを持ちながらも、汎用性の高いスキルを磨いていくことが、必要とされる人材になるための近道です。
なお、ポータブルスキルの詳細については↓の記事でも紹介しています。
より詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。
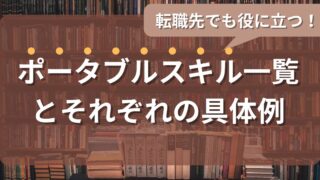
まとめ
本日は、仕事に頼りにされなくて不安な人に、会社から求められる人材になるための方法を紹介しました。
- ポイント①:自分の価値を提供する相手・分野を決める
- ポイント②:相手の求めることを解決する方法を決める
- ポイント③:自分の価値をコンテンツとして作り出す
- ポイント④:作り出した価値を伝える
- ポイント⑤:ポータブルスキルを身につける
これからの時代において必要とされる人材は、「受け身で与えられた仕事をこなす人」ではなく、「主体的に考え行動し、価値を生み出す人」です。
積極性や柔軟な対応力、他者と協力する姿勢、多様性への理解など、時代とともに人材に求められる資質は大きく変化しています。
「必要とされる人材」とは、自分の強みを自覚し、それを周囲や社会に適切に提供できる人のことです。
時代の変化をチャンスと捉え、自分の価値を高めていきましょう。
以上、タカヒデでした。